年末が近づくにつれ、多くの企業が「働き方」の見直しを始めています。特に、人手不足や繁忙期・閑散期の波がある業種では、「1年単位の変形労働時間制」の導入を検討する企業が増えています。
年間休日105日以上ありますか?まず知っておきたい変形労働時間制の基本
制度の目的と概要をわかりやすく解説
1年単位の変形労働時間制とは、年間を通じて労働時間を平均し、繁忙期には長く、閑散期には短く働ける制度です。月ごと・週ごとの労働時間が変わっても、年間の平均が法律の範囲内であれば認められます。
導入することで得られるメリットとは?
業務量の変動が大きい業種では、残業代の抑制や、労働力の有効活用が可能になります。また、従業員にとっても閑散期に休みを取りやすくなるなどのメリットがあります。
導入に必要なステップと注意点
就業規則の変更と労使協定の作成
まずは制度導入のために、就業規則へ「変形労働時間制を採用する」旨を記載します。また、労働者の過半数代表者と「労使協定」を結ぶ必要があります。
労働基準監督署への届出とそのタイミング
作成した労使協定は、所轄の労働基準監督署へ届出が必要です。届出がない状態で運用すると、法令違反とされる可能性があります。
【各務原市対応】中小企業での導入事例と現場の声
製造業・小売業など、地域企業の活用例
例えば製造業では、夏や年度末の繁忙期に合わせて長時間労働を設定し、閑散期に休日を多く取る運用がされています。小売業でも、土日・祝日に集中する勤務体制に対応しやすくなります。
社労士が見た、導入でつまずきやすいポイント
代表者が労使協定の届出を忘れていた、労働者代表の選出が適切でなかった、カレンダー作成が雑だった等、細かい部分でのミスが多く見られます。
導入を検討する企業に向けたチェックリスト
現在の働き方に合っているか?
繁閑の差が明確にある、月によって勤務時間にばらつきがある等の特徴があるかを見直します。
変形制に向いている業種・職種とは?
製造業・小売業・介護業界など、一定期間に業務が集中する職場での導入が特に有効です。
社労士に相談するメリットとは?
制度設計・書類作成・監督署対応の安心サポート
就業規則の改定やカレンダー作成、労使協定の内容精査、提出書類の作成など、専門家がサポートすることでスムーズに進められます。
まとめ|各務原市の企業が今から取り組むべきこと
令和8年度を目前に控え、働き方改革と生産性向上の両立が求められる今、制度導入の準備は「年末がチャンス」です。正しく導入し、トラブルを未然に防ぐためにも、社会保険労務士への早めのご相談をおすすめします。

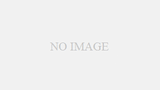
コメント